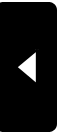› しぇりの素 › 黒い白鳥
› しぇりの素 › 黒い白鳥2010年07月25日
黒い白鳥
 以下は、谷藤友彦さんという、「エム・アイ・アソシエイツ(MIA)株式会社」という会社で、組織変革・人材育成に関するコンサルティングおよび研修サービスをしていらっしゃる中小企業診断士の方のブログです。
以下は、谷藤友彦さんという、「エム・アイ・アソシエイツ(MIA)株式会社」という会社で、組織変革・人材育成に関するコンサルティングおよび研修サービスをしていらっしゃる中小企業診断士の方のブログです。『ブラック・スワン』という本について、書評めいた論理を書かれています。・・・が、コムズカシイのと長い
 のとで、しぇりがちょっと気になる部分だけご紹介、もとい使わせていただこうかな・・・と思います
のとで、しぇりがちょっと気になる部分だけご紹介、もとい使わせていただこうかな・・・と思います
人間の理性の限界を徹底的に茶化してるな-『ブラック・スワン』
ブラック・スワン[上]・[下]―不確実性とリスクの本質
ナシーム・ニコラス・タレブ
ダイヤモンド社
2009-06-19
一言で言えば、「帰納的推論」の限界を論じた本。タイトルのブラック・スワンは直訳すれば「黒い白鳥」であるが、我々は経験則として白鳥は白いと思っている。だが、ある日突然「黒い白鳥」が発見されたとしよう。すると我々の頭はパニックだ。生物学者は過去の研究を再検証しなければならないし、生物図鑑を発行する出版社は原稿の書き直しを迫られる。それに、「白鳥の湖」を踊っている世界中のバレエ団は、果たして今後も白い衣装でステージを続けていいのかどうか、喧々囂々の議論を繰り広げることになるだろう。たかが黒い白鳥とあなどるなかれ、その影響は計り知れないのだ。
つまりブラック・スワンとは、帰納的推論から導かれた一般法則に当てはまらない例外事象であり、かつその影響が非常に大きいという特徴をもつ。我々は帰納的推論によって未来を予測しようとする。しかし、ブラック・スワンの存在があるために、未来を予測することは不可能であると著者は再三注意を喚起している。例え専門家であっても、素人よりも正確に未来を言い当てることができるという証拠はどこにもないとさえ著者は言う。
上記のことは、帰納的推論につきまとう限界としてはごくごく当たり前の話ではある。だが、あまりにも我々が帰納的推論に頼りすぎており、しかもブラック・スワンが現れると狼狽しながらも何とかそれを新しい法則でうまく説明しようとするいい加減な態度に著者は相当業を煮やしているようで、本の至るところで怒りをぶちまけている。その展開が痛快で面白い。ただ、個人的に下巻は正直要らなかったかな?上巻だけでも十分な内容であり、下巻は読みながらちょっと食傷気味になってしまった。
完全な演繹的推論が成り立つのは、数学や法の世界など一部に限られている。
(中略)
ただし、いくら科学者が厳密に設定した法則であっても、そしてそれらを演繹的に活用して新たな法則を生み出したとしても、スタートラインにおいて帰納的推論に従っている限り、いつでもブラック・スワンの脅威が立ちはだかる。ひとたびブラック・スワンが現れれば、過去の法則を再検証し、新たな法則を打ち立てなければならない。自然科学はいつの時代にもそうやって発達してきた。
同じことが社会科学であるマネジメントにも当てはまる。マネジメントの原理原則は、成功企業や失敗事例の観察、職場や工場での実験を通じて得られた事実の積み重ねから確立されている。言い換えれば、マネジメントの法則は自然科学の場合と同様に、その発見段階では帰納的推論に拠っている。これらの法則が多くのビジネスパーソンから正当性を認められると、今度はその法則が演繹的推論に用いられるようになる。
(中略)
経営環境は常に変化しており、いつ何時ブラック・スワンが目の前に現れるか解らない。過去の法則が未来永劫使える保証はどこにもない。ブラック・スワンを一時的な例外だと過小評価して、過去の因習にしがみつく企業は死に絶えるだろう。逆に、ブラック・スワンをうまく味方につけることができれば、競合他社を出し抜いて大きな成功をもたらすかもしれない。
懐疑主義に立って早計な判断を留保し、事実をよく観察すること。特にリーダーは、さながら人類学者のように先入観を捨てて現実世界と対峙し、自分や自社のこれまでの成功を脅かしかねない例外的事象に目を光らせなければならないだろう。
・・・な、長い

劇薬は、薬と毒の紙一重です。ブラック・スワンも、捉え方と使い方で凶器にも武器にもなる・・・だから今までの成功や古い考え方(法則)に囚われず、事実をよく見て自分の『勝ち』の法則を打ち立てよ・・・そういうことですかね?
日々、教えていただいていることに近いので、寝ずに最後まで読めました
 そんな話しを聞かせてもらえる我々は、幸せ者だなぁ・・・。
そんな話しを聞かせてもらえる我々は、幸せ者だなぁ・・・。Posted by しぇり at 00:17│Comments(0)